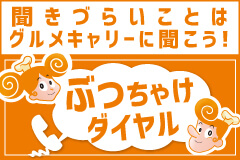所得税の仕組み
勤めていたときに毎月給料から天引きされていた源泉所得税は、「仮の税額を徴収されていた」という事になります。正確な税額は年末に一年間の給料総額が確定してから計算されます。正確な税額よりその年に天引きされていた合計額の方が多ければ還付され、少なければ追加で徴収されます。
この精算手続きを年末調整といい、12月31日に在職している人を対象に、勤務先がやってくれました。
新しい勤め先で年末調整をやってくれます。そのためには前の勤め先の源泉徴収票が必要ですので、辞めるときに受け取っておかなければいけません。
・退職した年に再就職なかった場合自分で精算手続きをしなければいけません。これを確定申告といいます。このときにも、源泉徴収票が必要です。
自分で税務署に行き手続きをするのは面倒ですが、多くの場合は納めすぎた税金が還付されますので、必ず行いましょう。
なお、雇用保険の基本手当には、所得税はかかりません。
住民税の仕組み
住民税は、前年の所得に基づいて税額が計算され、6月から翌年の5月にわたって、給料から天引きされます。
具体的には、平成30年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて税額が計算され、令和元年6月から令和2年5月までの給料から天引きされることになります。この場合、平成31年1月1日に住んでいた市区町村に納めることになり、途中で引っ越しても納付先は変わりません。
天引きされている途中で退職した人は、退職した月によって扱いが異なります。
→退職後に自分で納付
残りの住民税は、原則として個人で納付することになり、市区町村から自宅に納付書が送られてきます。
・1月から5月までに退職した場合→5月までの残額を一括で天引き
残りの全額が一括で天引きされます。例えば、1月に退職したなら5ヶ月分徴収されることになります。
退職金が支給された場合
退職金の支給額から勤務年数によって定められた控除額を引いたあとに課税されますが、実際にはよほど高額な退職金でなければ税額0円となるケースが多いでしょう。
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合退職金の支給額や勤務年数にかかわらず、一律20%の税額が源泉徴収されます。